 |
| Alfred Stieglitz |
写真家であり画商でもあったアルフレッド・スティーグリッツほど、20世紀のアメリカの芸術や文化に強い影響を与えた人物はいないだろう。南北戦争中の1864年にニュージャージー州のホーボーケンに生まれ、1946年まで生きたスティーグリッツ。ベルリンでの学生時代に写真を撮り始め、著名な光化学者であるヘルマン・ヴィルヘルム・フォーゲル(1834–1898)に師事した。1890年に帰国したスティーグリッツは、写真を芸術として扱うべきだと主張し始めた。1902年には、写真の芸術性を確立するための写真家の組織「フォトセセッション」を結成する。スティーグリッツは25年以上にわたってニューヨークを撮影し、街並みや公園、新しく出現した高層ビル、馬車、トローリー、列車、フェリーボート、そして人々の姿を描いてきた。また、1910年代後半から1920年代前半にかけては、ニューヨーク州のジョージ湖にある別荘周辺の風景にもカメラを向けていた。1918年、後に妻となる画家ジョージア・オキーフの撮影に夢中になった。長い間、一人の人間を長期間にわたって撮影する、いわゆるコンポジットポートレイトを撮りたいと考えていたのである。それから19年の間に、彼は330枚以上の彼女のポートレートを完成させた。
1922年から1920年代にかけて、もうひとつの主題である「空の雲」に夢中になり、300点以上の習作を完成させた。スティーグリッツは、2つの世界大戦、世界大恐慌、そしてアメリカが農村の農業国から工業国、文化大国へと成長していく過程など、アメリカがこれまで経験してきた最も大きな変化のいくつかに立ち会った。しかし、さらに重要なことに、彼はこれらの変化のいくつかをもたらすことに重要な役割を果したことである。パブロ・ピカソ(1881–1973)アンリ・マティス(1869–1954)ジョルジュ・ブラック(1882–1963)ポール・セザンヌ(1839–1906)などの作品を、1905年から1917年まで運営していた五番街291番地の「リトル・ギャラリー・オブ・ザ・フォト・セセッション」、1925年から1929年まで運営していた「インティメート・ギャラリー」、1929年から1946年まで運営していた「アン・アメリカン・プレイス」など、ニューヨークのギャラリーを通じ、ヨーロッパの近代美術をアメリカで初めて展示したのである。
またジョージア・オキーフ(1887–1986)アーサー・ダブ(1880-1946)ジョン・マリン(1870-1953)マースデン・ハートリー(1877-1943)チャールズ・デマス(1883-1935)など、アメリカのモダニズム芸術家たちを支援した。スティーグリッツにとって写真は常に中心的な存在だった。それは、彼が自分自身を表現するために用いたメディアであるだけでなく、より根本的には、彼がすべての芸術を評価するための試金石でもあった。コンピューターやデジタル技術が、今世紀の私たちの生活だけでなく、思考をも支配することが明らかになっているように、スティーグリッツもまた、同時代の多くの人々よりもずっと早く、写真が20世紀の文化的な主要勢力となることを認識していた。
彼が「写真のアイデア」と呼んだものに魅了され、写真が学習やコミュニケーションの方法のあらゆる面に革命をもたらし、すべての芸術を大きく変えることを予見していたのである。スティーグリッツが写真というメディアを理解する上で中心となったのは、彼自身が撮影した写真であり、写真の表現力や他の芸術との関係性を探るための道具だった。彼が写真を撮り始めた1880年代初頭、写真というメディアはまだ40年も経っていなかった。しかし、スティーグリッツが1937年に体調を崩して写真撮影を中止した頃には、写真とそれに対する一般の人々の認識は大きく変わっていた。『カメラノート』『カメラワーク』『291』などの出版物、自ら企画した展覧会、そして明快で洞察に満ちた自らの写真によって、スティーグリッツは写真というメディアの表現力を決定的に示したのである。
 Alfred Stieglitz (1864–1946) Photography Collection | The Art Institute of Chicago
Alfred Stieglitz (1864–1946) Photography Collection | The Art Institute of Chicago





 プラハのカレル橋(Charles Bridge)チェコ共和国観光局オフィシャルブログ(日本語)
プラハのカレル橋(Charles Bridge)チェコ共和国観光局オフィシャルブログ(日本語)




 Josef Sudek (1896-1976) Biography and Collected Photographs | The Baruch Foundation
Josef Sudek (1896-1976) Biography and Collected Photographs | The Baruch Foundation





 Robert Capa (1913–1954) Color Photographs | International Center of Photography
Robert Capa (1913–1954) Color Photographs | International Center of Photography





 Eugene Smith Online Collection | Center for Creative Photography | University of Arizona
Eugene Smith Online Collection | Center for Creative Photography | University of Arizona





 Diane Arbus (1923–1971) Archived Photographs | The Metropolitan Museum of Art
Diane Arbus (1923–1971) Archived Photographs | The Metropolitan Museum of Art



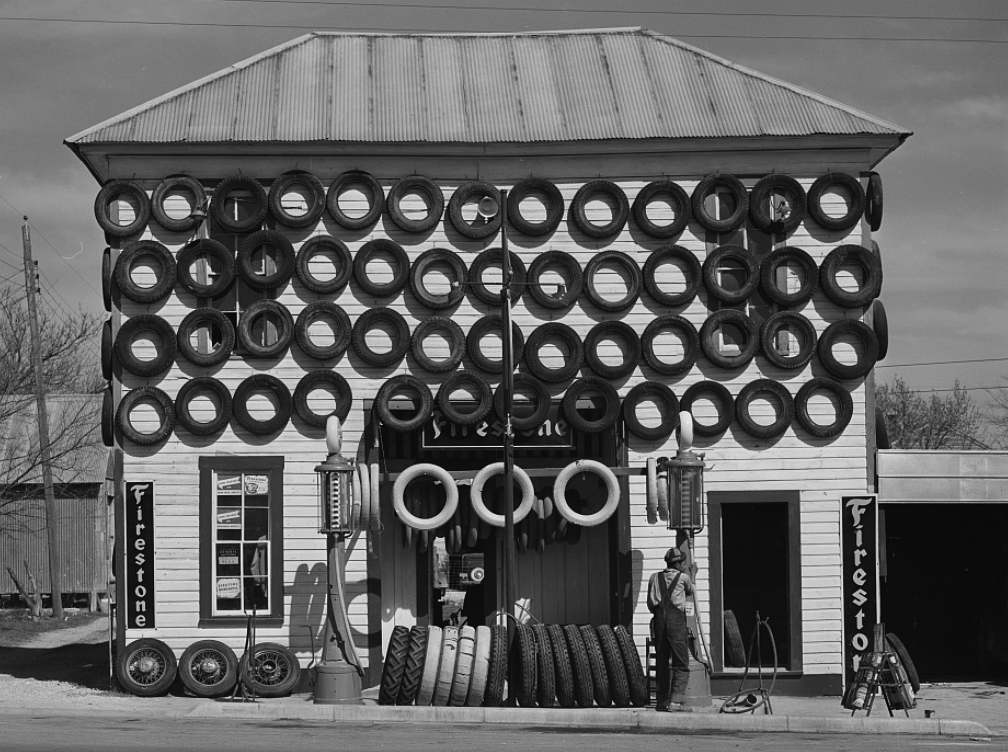






 Une archive de l'œuvre du père réalisée par ses deux filles | Atelier Robert Doisneau
Une archive de l'œuvre du père réalisée par ses deux filles | Atelier Robert Doisneau



