これまで私が触れた何冊かの本、例えばジェイムズ・ジョイス『ダブリン市民』、ギルバート・ホワイト『セルボーンの博物誌』、W・H・ハドスン『はるかな国とおい国』などに共通していること、それは正直言って読み疲れるということである。少し読んでは放り出し、また忘れたころに読み進める。ヘンリー・D・ソロー『森の生活』もそうだが、ハーマン・メルヴィル『白鯨』(モビィ・ディック)がその極めつきではないだろうか。とにかく通読するだけでも厄介で、私は何度も挫折、数カ月を費やしてやっとのことで読み終えたのだった。物語のクライマックス、エイハブ船長と白鯨モビィ・ディックの闘いにたどり着くまでの道程が長いのである。著者メルヴィル(1819-1891)は実際に捕鯨を体験している。したがって見方を変えれば、ここに書かれている当時の鯨学、捕鯨業の実態、あるいは船員の生活など、貴重な記録文学と言える。18世紀~19世紀半の欧米諸国による捕鯨は鯨油を採ることが主目的だった。そして浦賀へ来航したペリーの艦隊の黒船が、江戸幕府に開港を迫ったのは、アメリカの捕鯨船団が燃料や食料補給のために寄港したかったからだという。
 |
| C・W・ニコル『勇魚(上・下)』(文春文庫)1992年 |
作家のC・W・ニコルさんが2020年4月3日、直腸がんのため長野市の病院で死去した。著書『勇魚(いさな)』を思い出し、読み返してみたが、これは一気に読破することができた。舞台は和歌山県太地、今でも捕鯨の町である。幕末。おりしも井伊直弼、吉田松陰、坂本龍馬などが世界に目を転じ始めたころだった。エイハブ船長は白鯨によって片足を失ったが、この小説の主人公、甚助は鯨に片腕を奪われている。失意のどん底にあった彼に声を掛けたのが紀州藩士、松平定頼だった。定頼は黒船の出現を知り、海防の必要性を幕府に説き、甚助を密偵に仕立てる。紆余曲折の末、ジョン万次郎に出会った甚助はジム・スカイの名で海外に雄飛する。波乱に飛んだ歴史物語だが、作者のニコルさんはよくここまで調べたものだと感心する。ウェールズ出身で、1995年に日本に帰化したが、一年間太地に暮らした経験があるという。その体験ゆえに書けたのだろうが、訳者あとがきにもあるが、私も鯨を勇魚(いさな)と呼ぶことは知らなかった。勇ましい魚という意味である。鯨は魚類ではなく哺乳類だが、中国語では鯨魚と表記する。万葉集に「鯨魚取海哉死為流山哉死為流死許曽海者潮干而山者枯為礼」(第16巻第3852番)という歌がある。鯨魚(いさな)取り海や死にする山や死にする死ぬれこそ海は潮干て山は枯れすれ。つまり「海は死ぬだろうか、山は死ぬだろうか。死ぬからこそ海は潮が干し上がるし、山は草木が枯れる」という摂理を詠んでいるのである。
太地を初めて訪れた松平定頼は獲れた鯨の解体作業に立ち会う。太地角右衛門(網捕り式捕鯨の考案者)は漁師たちが鯨の霊に祈ったことに対し「わたしどもとて死の悲しみは感じますが、しかしその悲しみの一方に、海からあのような恵みを受けるよろこびもあり、わたしどもはなにひとつむだにいたしませぬ。肉、油、骨、髭、すべてを使います」と定頼に答える。さらに臓物も食べると答えながら「正直申して、わたしは肉のほうが、わけても尾に近い脂ののった肉が好きです」と説明する。これは鯨の尾の身、すなわち尾の背側の部分の脂が霜降りになった部位を指す。一昨年の暮れ大阪道頓堀の『たこ梅』でサエズリ(ヒゲクジラの舌)の煮込みを食べた話を書いた。これも絶品だが、尾の身の刺身はさらに素晴らしい。私はアメリカの海洋哺乳類保護団体のメンバーと会ったことがある。鯨の肉は物凄く美味しいよと話したら、彼らが目を丸くしていたのを思い出した。国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退を表明したことで、2019年、1988年以来、30年ぶりに商業捕鯨を再開した。南極海での捕鯨を停止することは歓迎するが、鯨肉の供給に問題が出そうである。しかし鯨肉はもはや食道楽のための高級食材であり、もはや日本人の蛋白源ではないことを改めて再認識すべきだろう。
 大崎晃「19世紀後半期アメリカ式捕鯨の衰退と産業革命」東京地学協会(PDFファイル 1.29MB)
大崎晃「19世紀後半期アメリカ式捕鯨の衰退と産業革命」東京地学協会(PDFファイル 1.29MB)








 Ferdinando Scianna (born 1943) | Profile | Highlight | Most Recent | The Magnum Photos
Ferdinando Scianna (born 1943) | Profile | Highlight | Most Recent | The Magnum Photos



 Ellis Island | Immigration and Relocation in United States History | Library of Congress
Ellis Island | Immigration and Relocation in United States History | Library of Congress

 TuneIn Radio: Music & Sports | Stream Radio from Stream Japan | Free Internet Radio
TuneIn Radio: Music & Sports | Stream Radio from Stream Japan | Free Internet Radio



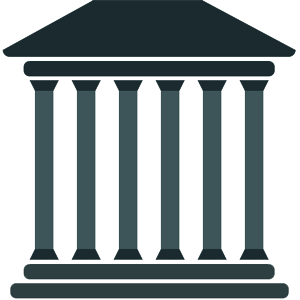 Stereo-graphoscope | Graphic Arts Collections, Firestone Libraly, Princeton University
Stereo-graphoscope | Graphic Arts Collections, Firestone Libraly, Princeton University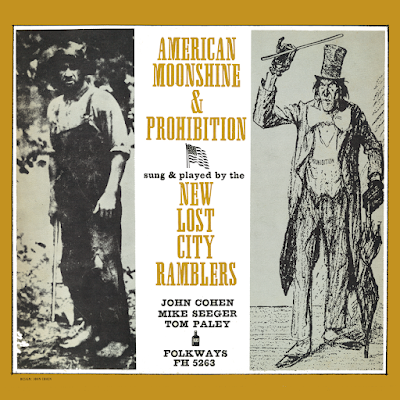





 The heartbreaking, controversial history of Mount Rushmore National Monument, 2020
The heartbreaking, controversial history of Mount Rushmore National Monument, 2020


 Why do we communicat on social media in English rather than in our Primary Language ?
Why do we communicat on social media in English rather than in our Primary Language ?

 Harmas Jean-Henri Fabre | Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Harmas Jean-Henri Fabre | Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
 YAMANEKO RESEARCH INSTITUTE | PROFILE | BOOKS | REPORTS | NEWS | CONTACT
YAMANEKO RESEARCH INSTITUTE | PROFILE | BOOKS | REPORTS | NEWS | CONTACT



 IrfanView Official Homepage | One of the Most Popular Viewers Worldwide | Irfan Skiljan
IrfanView Official Homepage | One of the Most Popular Viewers Worldwide | Irfan Skiljan