小林清親『古今誠画 浮世画類考之内 慶長五年之頃 細川忠興室』1885(明治18)年
細川幽斎の長子忠興が建立した大徳寺塔頭高桐院は紅葉の名所で知られる。それゆえか真夏の参詣は初めてである。書院の奥に茶室松向軒(しょうこうけん)がある。忠興は江戸時代初期の武人として有名だが、三斎と号したように利休七哲に数えられる茶人でもあった。茶室の天井から小さな裸電球がぶら下がっている。その明かりを頼りに天井に目を注ぐ。実に質素なたたずまいだ。こういうのを利休風建築というのだろう。利休好みという言葉がある。ワビとかサビというのは、唐変木の私にとって理解できない気風だ。古寺にしても、風雪が変貌させた土や草の色はあまり好きではない。むしろ、金ピカだったり派手な朱色だたりしていたほうが嬉しい。伽藍が暗示する浄土はそんな世界ではないだろうか。備前焼きより清水焼きのほうが好きな私だ。高桐院は細川家の菩提寺でもある。西庭の一角に三斎の墓所がある。その墓石はガラシャ夫人のものだという。南庭の春日灯篭は、その墓石を模したものだという。
「奥方さま、では、お覚悟を。直ちにわれらこれより御供申しあげまする。しかしながら、このお傍に果てるのは余りにも恐れ多きこと故、われらは玄関にて御供させて頂きまする」「自害は許しませぬ。天主のみもとに行くは、わたくし一人にとどめますように。では、早う、少斎どの。頼みまする」「奥方ごめん!」閃くと見た少斎(小笠原秀清)の長刀が、一瞬のうちに玉子の胸を刺しつらぬいた。真紅の血がさっと飛び散り、玉子の上体がぐらりと前に傾いたかと思うと、そのまま玉子は床に打ち伏した。(三浦綾子『ガラシャ夫人』主婦の友社 1975年)
 |
笠の後ろが三分の一欠けた春日灯篭
高桐院(京都市北区紫野大徳寺町) |
家臣に首を切らせたという異説もある。ガラシャが自らの意志で散ったのは1600年8月25日(慶長5年7月17日)、辞世の句は「散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」だった。遺骨は大阪の崇禅寺の境内に埋葬されたという。10月、夫である忠興はオルガンチノ神父と相談して盛大なキリスト教式葬儀を行った。忠興が高桐院を建立したのがその翌年になる。この塔頭建立とガラシャとの関係はどうなっているのだろうか。暗雲からわずかにこぼれた光の束は、鬱蒼とした樹木のフィルターでさらにその力を弱めている。小さな門をくぐると、そこは廟になっていた。正面に石灯篭が見える。観光で訪れたのだろう、ふたりの女性の声が弾んでいる。これが忠興とガラシャの墓石なのだそうだ。千利休が秘蔵していた灯篭で「天下一」の称があったという。秀吉と忠興のふたりに請われて困った利休は、わざと笠の三分の一を欠き、キズ物と称してその懇請を断ったという。
キリシタン大名高山右近追放、ガラシャ受洗、キリスト教禁教令、三木パウロ殉教、秀吉の全国統一、家康江戸入城、そして長崎における二十六聖人の殉教と続く。1596年(慶長元)、千利休は秀吉によって自殺に追いやられている。利休の遺志によって灯篭「天下一」は細川忠興の手に渡った。5年後に建立したこの寺の庭に置いたのは間違いないだろう。しかし、この灯篭をもってすぐにガラシャの墓石にしたかどうかは歴史書は寡黙だ。夫人の死後、忠興は83歳で死ぬまで、45年も生きながらえた。かれは亡き夫人を偲んで、生涯再婚はしなかったという。その間に、自らと、そしてガラシャの墓石にこの石灯篭を転嫁させたのだろうか。明智光秀の謀反によってその玉子は一転「逆賊の娘」になってしまった。その玉子がなぜガラシャになったか、得も知れぬ興味が湧いてきたのに思わず身震いした。戦国時代を駆け抜けたキリシタンとはいったい何だったのだろうか。私は夢を見始めたようだ。あの灯篭はほんとにガラシャの墓石なのだろうか。この禅林は細川家の菩提寺だ。デウスに帰依したガラシャの痕跡はここにあるだろうか。細川家の紋は残っている。しかしここには十字架はない。ただあるのは利休好み、三斎好みの灯篭があるだけだ。キリスト教式の葬儀を行ったにも関わらず、その痕跡をこの庭に残さなかったのは何故だろうか。それがキリシタン史を紐解くひとつの鍵ではないだろうか。今日、宗教が現実世界に投下してる影響力は数知れなくある。宗教はひとつの方向性を持っているのが常だが、信心がない人間には理解できない。




 The official trailer "Coat of Many Colors" for Dolly Parton NBC Movie
The official trailer "Coat of Many Colors" for Dolly Parton NBC Movie




 新潮社の特設サイト「新潮文庫の100冊」2016
新潮社の特設サイト「新潮文庫の100冊」2016


 フライヤーの表示とダウンロード(PDFファイル 693KB)
フライヤーの表示とダウンロード(PDFファイル 693KB)










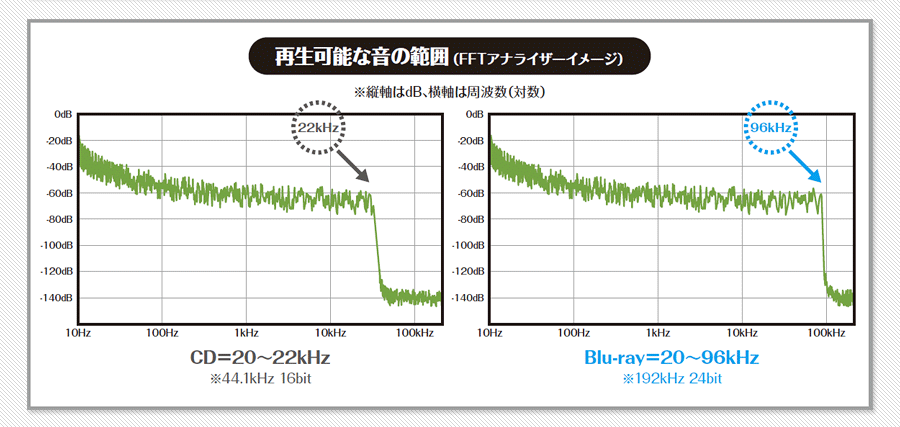



 伊藤比呂美編『石垣りん詩集』(岩波文庫2015年)
伊藤比呂美編『石垣りん詩集』(岩波文庫2015年)


 祇園祭2016年(京都市産業観光局観光MICE推進室)
祇園祭2016年(京都市産業観光局観光MICE推進室)